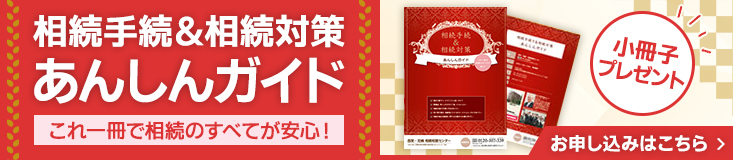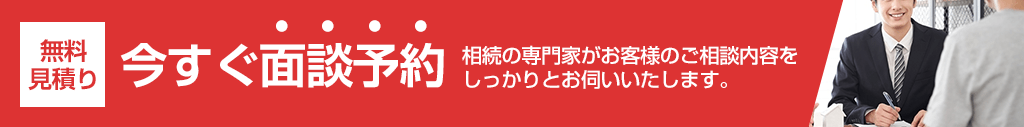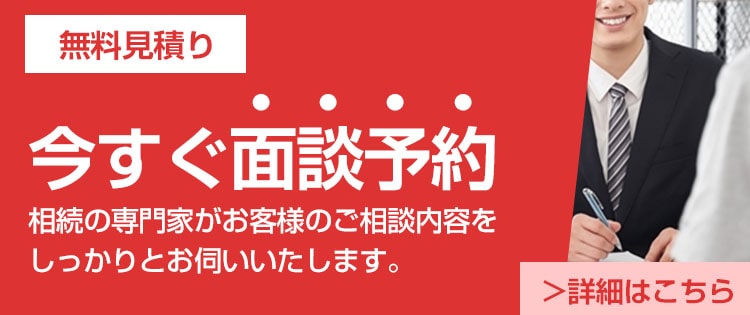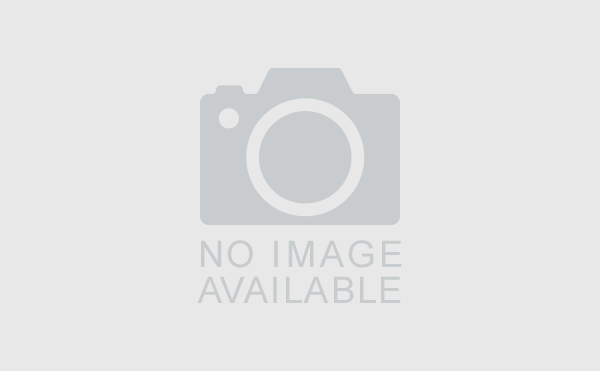尼崎の相続税理士が教える!「配偶者の税額軽減措置を活用して相続税を減らす方法」
こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
相続税の中でも、特に大きな節税効果が期待できる制度が「配偶者の税額軽減」です。
これは、配偶者に対して相続税の負担を大幅に軽くする特例で、うまく活用すれば相続税がゼロになるケースもあります。
今回は、この制度の内容と活用方法についてわかりやすく解説しますね。
1. 配偶者の税額軽減とは?
配偶者が相続する財産について、以下の範囲まで相続税がかからないという特例です。
✓ 法定相続分まで
✓ または 1億6,000万円までのどちらか大きい額
つまり、配偶者が1億6,000万円以内の財産を相続した場合は、たとえ全体の遺産が多くても、配偶者には相続税が課税されません。
2. 具体例で確認してみよう
被相続人(夫)の遺産:2億円
相続人:妻と子1人(法定相続分は妻1/2、子1/2)
この場合、妻が1億円を相続すれば、それは法定相続分以内かつ1億6,000万円以下なので、妻の相続税はゼロになります。
一方、子には1億円の相続があり、こちらに対しては通常通り相続税がかかります。
3. 適用には申告が必要!
注意したいのは、「配偶者の税額軽減」を使うには相続税の申告が必要という点です。
「非課税だから申告も不要」と思われがちですが、申告をしないと軽減措置が適用されません。
たとえ配偶者の税額がゼロであっても、必ず申告書を提出しましょう。
4. 軽減措置のメリットと落とし穴
【メリット】
✓最大1億6,000万円まで非課税
✓自宅や預貯金など、大きな財産を無税で承継できる
✓一次相続(夫→妻)の税負担を大幅に減らせる
【注意点】
✓妻がすべて相続すると、将来の「二次相続」(妻→子)の際に相続税負担が大きくなる可能性があります。
✓遺産分割のバランスを見極めて、長期的な相続対策が必要です。
5. 節税の鍵は“計画的な分割”
配偶者の税額軽減は強力な制度ですが、それだけに頼りすぎると次世代の相続時に負担が集中することがあります。
相続税は「総額」ではなく「取得した人ごと」に課税されるため、配偶者・子・孫などへの分配バランスが大切です。
まとめ
✔ 配偶者の相続は、1億6,000万円 or 法定相続分まで非課税
✔ 適用には相続税の申告が必須
✔ 節税だけでなく、次の相続まで見据えた対策が重要
いかがでしたでしょうか?
一時的な税負担の軽減だけでなく、将来の相続も見据えたトータルの対策を検討されたい方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。
無料相談実施中!
相続手続きや相続税の申告、生前贈与等についてお悩みのことがありましたら、
西宮・尼崎相続相談センターにお気軽にご相談ください。
相続に強い税理士が、親身になってサポートいたします。
まずはメールかお電話で無料相談をご予約ください。
オンライン・対面で30分程度お話をお伺いした後、無料でお見積りいたします。