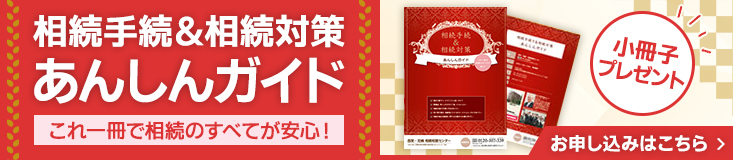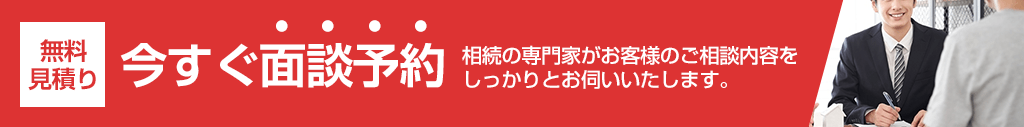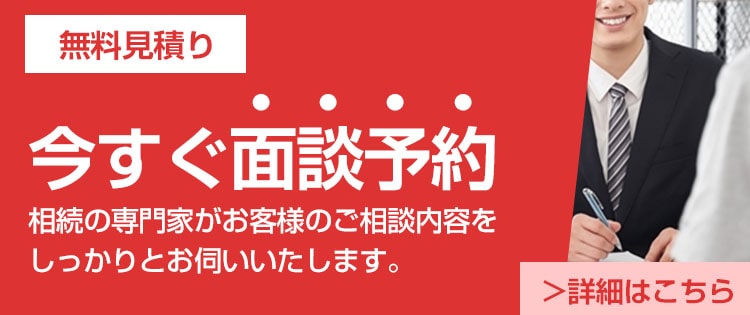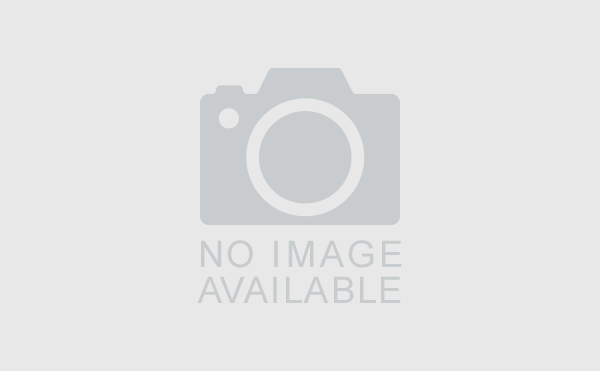尼崎の相続税理士が教える!「相続税の申告書作成のポイントと必要書類一覧」
こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
相続税の申告は、相続開始(通常は被相続人の死亡)から10か月以内に行う必要があります。
期限を過ぎると延滞税や加算税が発生するため、早めに準備を始めることが大切です。
今回は、申告書作成の流れと注意点、そして提出に必要な主な書類を整理してご紹介しますね。
1. 申告書作成の流れとポイント
■ ステップ①:財産の把握と評価
遺産の内容を洗い出し、不動産、預貯金、株式、生命保険など、すべての財産を評価します。
不動産は路線価、預金は残高証明などをもとに評価します。
■ ステップ②:債務・葬式費用の整理
借入金、未払金、葬儀費用などを差し引くことで「正味の遺産額」を算出します。
■ ステップ③:基礎控除額の確認
基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。
これを超える部分が課税対象になります。
■ ステップ④:遺産分割と税額計算
誰が何をどのくらい相続するかを決め、それぞれの相続税額を算出します。
配偶者の税額軽減や未成年者控除などの特例が使える場合は忘れずに適用しましょう。
■ ステップ⑤:申告書の作成と提出
相続税申告書(第一表~第15表など)を作成し、被相続人の住所地の税務署に提出します。
2. 必要書類一覧
申告には、次のような書類を揃える必要があります。
【基本書類】
・被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
・相続人の戸籍謄本
・住民票(被相続人・相続人)
・遺言書や遺産分割協議書(ある場合)
・印鑑証明書(相続人分)
【財産関係書類】
・不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書
・預金残高証明書(死亡日時点)
・株式・有価証券の残高明細
・生命保険の支払通知書
・借入金の残高証明書
・葬儀費用の領収書
3. よくある注意点
・遺産分割が未了の場合:特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例)が使えません。
早めの話し合いが重要です。
・財産の漏れ:小さな財産でも記載漏れがあるとペナルティの対象になります。
通帳の動きや保険証券の有無など、徹底的にチェックをしましょう。
・提出先の確認:申告は被相続人の死亡時の住所地の税務署に提出します。
まとめ
相続税の申告書は、財産の正確な把握と丁寧な書類整理がカギです。
必要書類は多岐にわたるため、相続開始後は早めに準備に取りかかりましょう。
いかがでしたでしょうか?
相続の必要書類は多岐にわたるため、判断が難しい部分については、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。
無料相談実施中!
相続手続きや相続税の申告、生前贈与等についてお悩みのことがありましたら、
西宮・尼崎相続相談センターにお気軽にご相談ください。
相続に強い税理士が、親身になってサポートいたします。
まずはメールかお電話で無料相談をご予約ください。
オンライン・対面で30分程度お話をお伺いした後、無料でお見積りいたします。