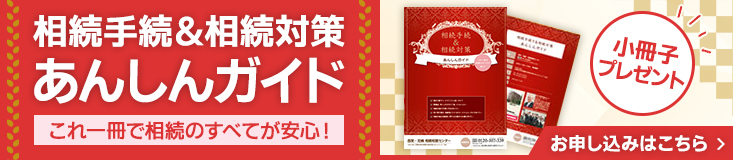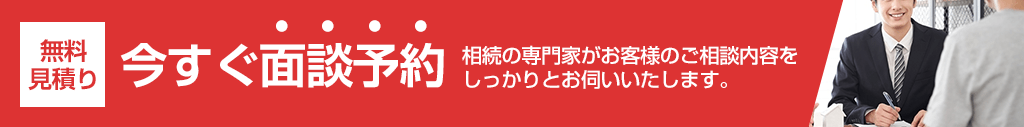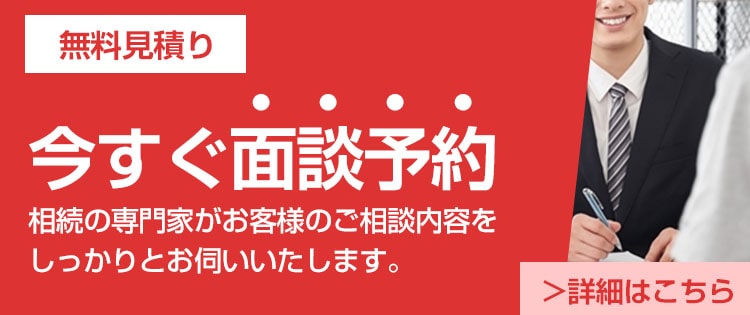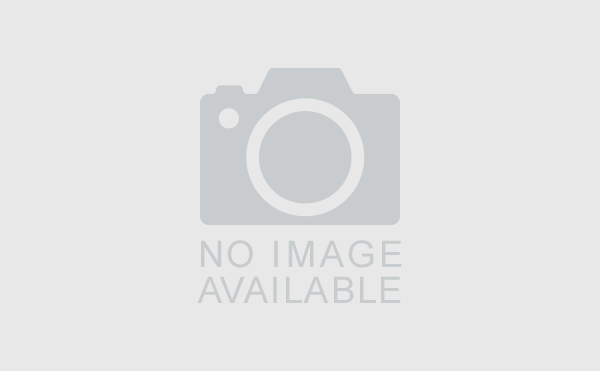尼崎の相続税理士が教える!「具体例で学ぶ!相続税の計算ステップと注意点」
こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
相続税の計算は複雑に見えますが、基本的な流れとポイントを押さえれば、全体像はつかめます。
今回は、具体例を使いながら相続税の計算ステップを解説し、注意すべき点についてもご紹介しますね。
1. 相続税の計算ステップ
【前提】
被相続人:父(死亡)
相続人:母と子2人(計3人)
遺産総額:8,000万円(不動産5,000万円、預貯金3,000万円)
ステップ①:課税遺産総額の計算
まず、「相続財産の総額」から「非課税財産」や「債務・葬式費用」などを差し引き、課税対象額を算出します。
ここでは、控除すべき債務や非課税財産がないものとして、
課税遺産総額=8,000万円
ステップ②:基礎控除の適用
相続税には以下の基礎控除があります。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
→ 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
従って、
課税対象額 = 8,000万円 - 4,800万円 = 3,200万円
ステップ③:法定相続分での按分
相続人が母と子2人の場合、法定相続分は以下の通り。
母:1/2 → 1,600万円
子:1/4ずつ → 各800万円
ステップ④:税率と控除額の適用(取得金額ごとに計算)
母(1,600万円)→ 税率15%、控除50万円
→ 1,600万円 × 15% - 50万円 = 190万円
子(各800万円)→ 税率10%、控除なし
→ 各800万円 × 10% = 80万円
合計税額:190万円 + 80万円 + 80万円 = 350万円
ステップ⑤:実際の相続割合に応じた負担に調整(必要に応じて)
実際の遺産分割が法定相続分と異なる場合は、それに応じて各人の税額が変わるため、正しい分割内容に基づいて再計算が必要です。
2. 注意したいポイント
■ 小規模宅地等の特例を見逃さない
自宅の土地などは、一定の要件を満たせば最大80%減額が可能です。
不動産の評価額が高い場合は、適用可否を必ず確認しましょう。
■ 生命保険金の非課税枠を活用する
「500万円 × 法定相続人の数」までは、保険金が非課税になります。
これも相続財産から除いて計算する必要があります。
■ 二次相続への配慮も大切
配偶者に多く遺すと今回の税負担は減りますが、将来の二次相続(母→子)で税負担が増える可能性があるため、バランスを考えた分割が重要です。
まとめ
相続税の計算は、「総額→控除→按分→税率適用」という流れを理解することがカギです。
具体例を参考に、必要な計算ステップと注意点を把握し、事前の準備や対策に役立てていきましょう。
いかがでしたでしょうか?
計算ステップを理解し、事前の準備や対策を検討したいという方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。
無料相談実施中!
相続手続きや相続税の申告、生前贈与等についてお悩みのことがありましたら、
西宮・尼崎相続相談センターにお気軽にご相談ください。
相続に強い税理士が、親身になってサポートいたします。
まずはメールかお電話で無料相談をご予約ください。
オンライン・対面で30分程度お話をお伺いした後、無料でお見積りいたします。