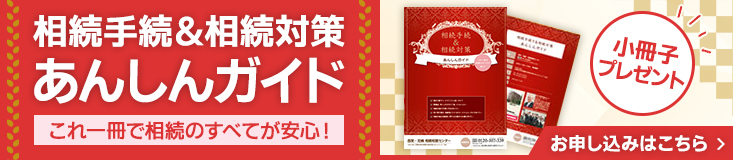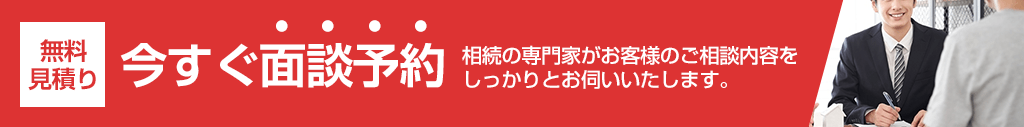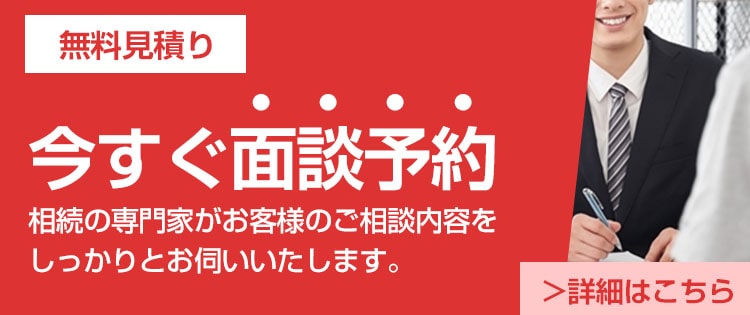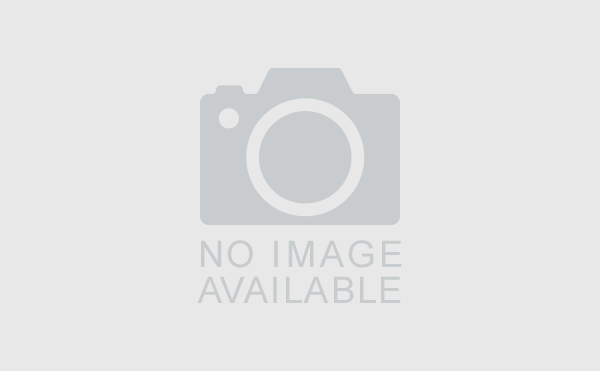尼崎の相続税理士が教える!「農地の相続税納税猶予制度とは?適用条件と手続きの流れ」
こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
農地は相続財産の中でも評価額が大きくなりやすく、相続税の負担が重くのしかかることがあります。
そんなときに役立つのが「農地の相続税納税猶予制度」です。
今回は、この制度について解説しますね。
1. 農地の納税猶予制度とは?
農業を継続する相続人に対して、農地にかかる相続税の納付を猶予する制度です。
農業を続けている限り納税は猶予され、一定の条件を満たして農業を続けたまま相続人が死亡した場合などには、
その相続税が最終的に免除されます。
2. 適用条件
納税猶予を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。
・対象となる農地
市街化区域を除く農地や、特定市街化区域内の一部の農地などが対象。
・相続人の要件
相続人が「農業相続人」として農業を引き継ぎ、相続税の申告期限までに農業委員会の証明を受けることが必要です。
・営農継続の義務
相続人が引き続きその農地で農業を営み、貸したり転用したりせず維持すること。
3. 手続きの流れ
① 相続税の申告
相続開始から10か月以内に相続税の申告を行い、その際に「納税猶予の適用を受ける旨」を申告書に記載します。
② 農業委員会の証明取得
相続人が農業を継続することについて、農業委員会から「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」を取得します。
③ 猶予の適用開始
条件を満たせば農地にかかる相続税の納付は猶予されます。
④ 継続要件のチェック
猶予を受けている間、定期的に農業委員会の確認を受け、営農が続いていることを証明する必要があります。
⑤ 免除または納付
相続人が死亡するまで農業を継続した場合は猶予税額が免除されますが、
営農をやめたり農地を手放した場合には、猶予されていた相続税を一括で納めなければなりません。
4. 注意点
・制度を利用するためには厳格な要件や書類提出が必要です。
・農業をやめると猶予税額に加えて利子税が課される場合もあるため、利用する際は長期的な営農計画を考えることが不可欠です。
まとめ
✔ 農地の相続税納税猶予制度は、農業を継続する相続人にとって強力な支援策
✔ 相続税は猶予され、最終的に免除される可能性もある
✔ 適用には農業委員会の証明や継続的な営農が必須
✔ 途中で営農をやめると猶予分をまとめて納付するリスクも
いかがでしたでしょうか?
農業を続ける意思がある方にとって、この制度は相続税負担を大きく減らせる有効な手段ですので、
専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。
無料相談実施中!
相続手続きや相続税の申告、生前贈与等についてお悩みのことがありましたら、
西宮・尼崎相続相談センターにお気軽にご相談ください。
相続に強い税理士が、親身になってサポートいたします。
まずはメールかお電話で無料相談をご予約ください。
オンライン・対面で30分程度お話をお伺いした後、無料でお見積りいたします。