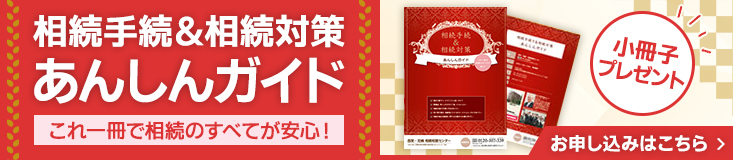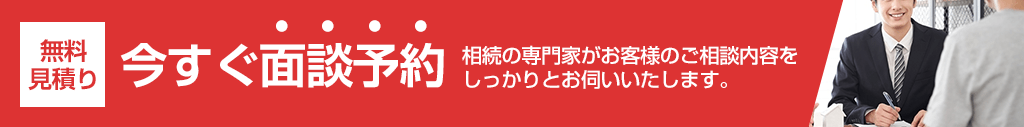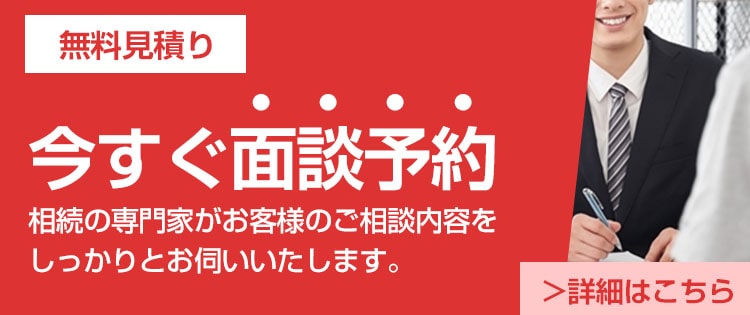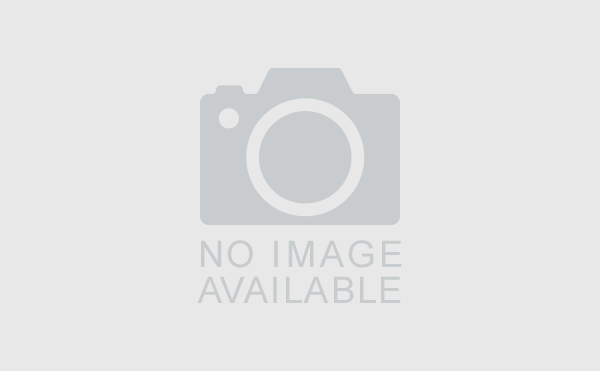尼崎の相続税理士が教える!「未成年者控除・障害者控除とは?適用条件と計算方法を解説」
こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
相続税には、遺族の生活や立場に配慮したさまざまな控除制度があります。
その中でも「未成年者控除」と「障害者控除」は、相続人が社会的に弱い立場にある場合に適用されるもので、相続税の負担を軽くできる重要な仕組みです。
今回は、この2つの控除の内容と計算方法を分かりやすく解説しますね。
1. 未成年者控除とは?
相続人が18歳未満の場合、社会的・経済的に自立していないことを考慮し、相続税から一定額が控除されます。
【控除額の計算式】
(18歳 − 相続開始時の年齢) × 10万円
例:相続時に15歳だった場合
(18歳 − 15歳)× 10万円 = 30万円 控除されます。
【注意点】
✓控除しきれなかった場合は、引ききれない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
✓未成年者控除を一度受けたことがあると、2回目以降の控除できる額が減額されます。
2. 障害者控除とは?
相続人が障害者手帳を持つなど、一定の障害のある人である場合には、こちらの控除が適用されます。
障害の等級により控除額が異なります。
【控除額の計算式】
・一般障害者:
(85歳 − 相続開始時の年齢) × 10万円
・特別障害者(重度の障害):
(85歳 − 相続開始時の年齢) × 20万円
例:相続時に60歳の一般障害者の場合
(85歳 − 60歳)× 10万円 = 250万円 控除されます。
【注意点】
✓85歳を超えている場合は、控除の適用はありません。
✓障害者手帳の写しなど、証明書類の添付が必要です。
3. 併用はできるか?
同一人物が「未成年者かつ障害者」の場合、両方の控除を併用できます。
たとえば、未成年で特別障害者の場合、それぞれの計算式を適用して合計額を控除できます。
4. 控除の適用には申告が必要
これらの控除を受けるには、相続税の申告書に必要事項を記入し、条件を満たすことを証明する書類(戸籍・障害者手帳など)を添付する必要があります。
「申告しないと適用されない」ため、該当する可能性がある方は、忘れずに確認しましょう。
まとめ
✔ 未成年者控除:18歳までの年数 × 10万円
✔ 障害者控除:85歳までの年数 × 10万 or 20万円
✔ 控除の適用には相続税の申告と証明書類が必要
いかがでしたでしょうか?
相続税には、個々の状況に応じた控除制度が整備されています。
対象となる相続人がいる場合は、申告時にしっかる活用するために、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。
無料相談実施中!
相続手続きや相続税の申告、生前贈与等についてお悩みのことがありましたら、
西宮・尼崎相続相談センターにお気軽にご相談ください。
相続に強い税理士が、親身になってサポートいたします。
まずはメールかお電話で無料相談をご予約ください。
オンライン・対面で30分程度お話をお伺いした後、無料でお見積りいたします。