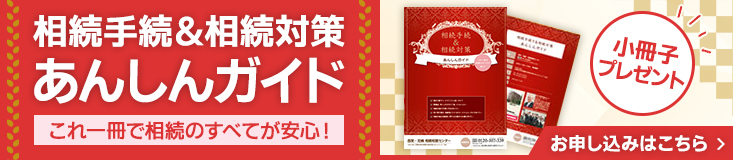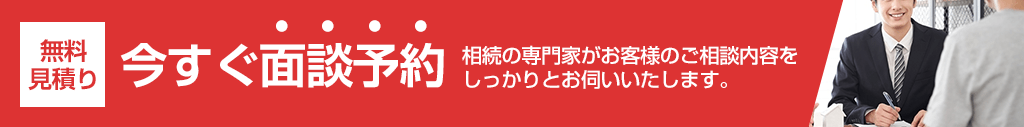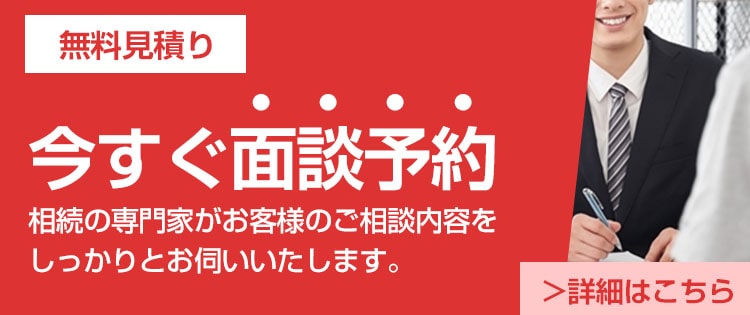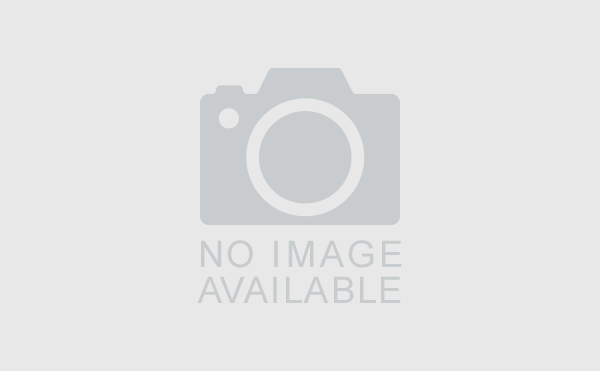尼崎の相続税理士が教える!「二次相続を見据えた相続税の計算と対策の重要性」
こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
相続税対策というと、多くの方が「一次相続(最初の相続)」ばかりに目を向けがちです。
しかし、より大きな税負担が生じる可能性があるのは「二次相続(配偶者の死後に発生する相続)」です。
今回は、この二次相続の重要性と対策のポイントを解説しますね。
1. 一次相続と二次相続の違いとは?
例えば、夫が亡くなった場合の相続が「一次相続」、その後、妻が亡くなった際の相続が「二次相続」です。
一次相続では、配偶者に対する税額軽減の特例(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)を使うことで、多くの場合、配偶者に相続税はかかりません。
しかし、全財産を配偶者が引き継いだ場合、その財産は将来の二次相続で課税対象となります。
2. 二次相続で税負担が増える理由
二次相続では、配偶者の税額軽減が使えなくなります。
また、法定相続人の数が減ることで基礎控除額が小さくなり、課税対象が増える傾向にあります。
例:
・一次相続(相続人:妻・子2人)→ 基礎控除 3,000万円 + 600万円×3人=4,800万円
・二次相続(相続人:子2人)→ 基礎控除 3,000万円 + 600万円×2人=4,200万円
つまり、同じ財産額でも二次相続の方が、税負担が重くなるケースが多いのです。
3. 二次相続を見据えた対策の例
■一次相続時に子にも財産を分ける
配偶者に集中させず、子にも適度に分けることで、二次相続時の課税対象を減らせます。
■生命保険を活用する
非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)を活かし、納税資金の準備や節税に有効です。
■遺言書で分割方法を明確に
将来の相続トラブルや無駄な課税を防ぐためにも、遺言書で配分を明確にしておくことが重要です。
■生前贈与の活用
暦年贈与や相続時精算課税制度を活用することで、長期的な財産の分散が可能になります。
まとめ
✔ 一次相続で税額を抑えても、二次相続では思わぬ課税が発生することも
✔ 二次相続の方が基礎控除が減り、配偶者軽減も使えないため注意が必要
✔ 一次相続から分割・贈与・保険などを活用し、長期的に対策を講じましょう
いかがでしたでしょうか?
相続は「二度」あるからこそ、初めの段階で将来を見据えた設計が大切ですので、円滑で無駄のない資産承継をしたいという方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。
無料相談実施中!
相続手続きや相続税の申告、生前贈与等についてお悩みのことがありましたら、
西宮・尼崎相続相談センターにお気軽にご相談ください。
相続に強い税理士が、親身になってサポートいたします。
まずはメールかお電話で無料相談をご予約ください。
オンライン・対面で30分程度お話をお伺いした後、無料でお見積りいたします。